2025.2.21
補聴器購入費用は年金受給者も医療費控除の対象に!医療費控除の申請方法や控除の金額も紹介


ご年齢を重ねるごとに、聞こえにくさを感じることはありませんか?ご家族のテレビの音量が気になりませんか?もしかしたら、それは補聴器が必要なサインかもしれません。
「でも、補聴器って高いんでしょ?」
「年金暮らしだと経済的に厳しいな…」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、補聴器の購入費用は医療費控除の対象になる場合があります。
この記事では、補聴器の医療費控除の申請方法や控除額について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、補聴器の購入を検討するきっかけにしていただけますと幸いです。
補聴器の購入費用は医療費控除の対象になる

補聴器は、聞こえに悩みを抱える方にとって、生活の質を向上させるための有効な手段です。最近では、認知機能との深い関わりがあるという研究も進められています。しかし、その一方で補聴器の購入費用は決して安くはありません。経済的な負担を理由に、補聴器の購入をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方に朗報です。補聴器の購入費用は、医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは、年間の医療費が10万円(※)を超える場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度です。
平成30年から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することで、医療費控除の対象となりました。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断された場合は一定の医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象としましては、国税庁から下記の発表がありました。
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられます。一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
ポイントとしては、補聴器が診療等のために直接必要か否かです。
補聴器が医師の診療に必要と証明できれば、医療費控除を受けることができます。
確定申告の際には、医師の診断書「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」と補聴器の領収書が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
※ 所得金額によって異なります。
補聴器購入の医療費控除は年金受給者も申請可能
補聴器購入費用で医療費控除を受けられる対象

補聴器の購入費用は、医療費控除の対象となる場合があります。ただし、誰でも控除を受けられるわけではありません。控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、大前提として医師による診療の結果、
補聴器の装用が必要であると診断される必要があります。
加齢による聴力低下や、病気やけがによる聴力障害などが挙げられます。
上記のような診断を受け、医師の指示に基づいて補聴器を購入した場合、その費用は医療費控除の対象となります。
また、この医師は、補聴器相談医の資格を持っている医師に限ります。
高齢者や年金受給者も対象になる
「医療費控除」と聞くと、現役世代を対象とした制度のように思えるかもしれません。
しかし、高齢者や年金受給者の方も、医療費控除を受けることができます。
年金収入のみで生活している方でも、確定申告を行うことで医療費控除を受けることが可能です。戻ってきる金額は所得や納税に応じて一人一人違うため、一度税務署や税理士にご確認いただくのをおすすめします。
補聴器の購入費用は高額になるケースもあるため、医療費控除を利用することで経済的な負担を軽減することができます。
聞こえに不安を感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診し、医師に相談してみましょう。
医師の診断に基づいて補聴器を購入する際には、医療費控除の対象となるかどうかを確認するようにしましょう。
確定申告の際には、医師の診断書「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」と補聴器の領収書が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
ご不明な点があれば、税務署や税理士にご相談ください。
補聴器購入費用の医療費控除の申請方法
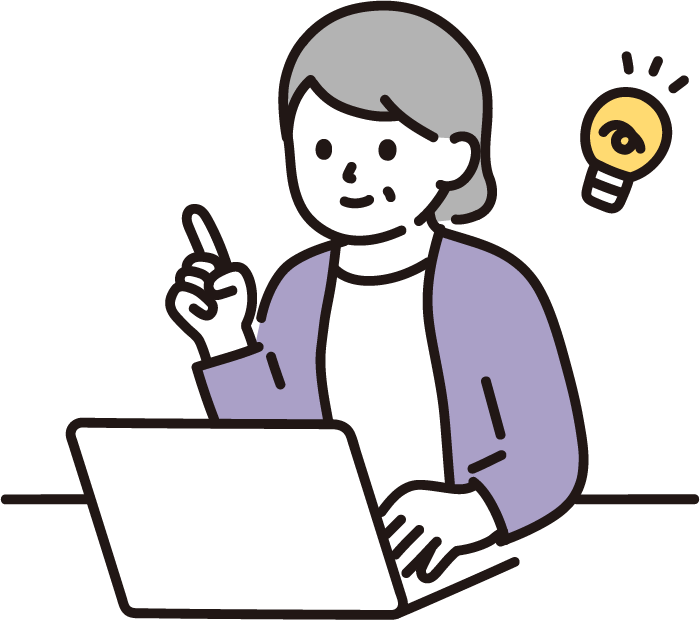
確定申告の準備
1.確定申告書
2.医療費控除の明細書
3.補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の写し
4.補聴器の領収書
確定申告の方法
1.税務署の窓口で提出する
2.郵送で提出する
3.e-Taxで提出する
補聴器の医療費控除についての還付時期

補聴器の購入費用の医療費控除を受けた場合、還付金がいつ頃振り込まれるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
還付金が振り込まれる時期は、確定申告の方法や時期によって異なります。
税務署の窓口で確定申告を行った場合
税務署の窓口で確定申告を行った場合、還付金は通常1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれます。
ただし、確定申告の時期や税務署の混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
郵送で確定申告を行った場合
郵送で確定申告を行った場合、還付金は通常2ヶ月~3ヶ月程度で振り込まれます。
郵送の場合も、確定申告の時期や税務署の混雑状況によって、さらに時間がかかることがあります。
e-Taxで確定申告を行った場合
e-Taxで確定申告を行った場合、還付金は通常1ヶ月程度で振り込まれます。
e-Taxは、オンラインで確定申告ができるため、税務署の窓口や郵送に比べて還付金が振り込まれるまでの期間が短い傾向にあります。
還付時期に関する注意点
還付金は、確定申告書に記載された金融機関の口座に振り込まれます。
口座情報に誤りがあると、還付金が振り込まれないことがありますので、注意が必要です。
また、確定申告の内容に不備があった場合や、税務署の審査に時間がかかった場合などは、還付金が振り込まれるまでに時間がかかることがあります。
還付時期が遅れる場合の対処法
確定申告を行ってから一定期間が経過しても還付金が振り込まれない場合は、税務署に問い合わせてみましょう。
税務署に問い合わせる際には、確定申告書控えや本人確認書類などを用意しておくと、スムーズに話が進みます。
ご不明な点があれば、税務署や税理士にご相談ください。
補聴器選びのポイント
補聴器選びは、聴力やライフスタイルによって異なります。また、補聴器は管理医療機器です。専門知識を持った認定補聴器専門店にご相談いただくのがおすすめです。
医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を受けるためには、医師の補聴器適合に関する情報提供書(2018)
と補聴器の領収書が必要です。
確定申告の際には、これらの書類を忘れずに提出しましょう。
ご不明な点があれば、税務署や税理士にご相談ください。
補聴器は、聞こえの改善だけでなく、生活の質を向上させるための有効な手段です。
医療費控除を賢く利用して、快適な聞こえを手に入れましょう
補聴器の修理や電池交換も医療費控除の対象?
「補聴器の購入費用は医療費控除の対象になる」ということは広く知られていますが、補聴器の修理費用や電池交換費用はどうなのでしょうか?
結論から言うと、基本的に補聴器の電池交換費用や修理費用は医療費控除の対象となりません。ただ、最終的な判断は税務署になります。お近くの税務署へお問い合わせください。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となるのは、あくまで「治療」を目的とした費用です。
補聴器の購入費用は、聴力低下を補うための治療費とみなされるため、医療費控除の対象となります。
しかし、電池交換費用は、補聴器の使用に必要な維持費であり、治療費とはみなされないため、医療費控除の対象とはなりません。
補聴器の修理費用も同様で基本的には医療費控除の対象にはなりません。
税務署の判断に分かれますので、医療費控除を受けたい場合は、修理を依頼する前に、税務署に確認することをおすすめします。
ヒヤリングストアでは、医療費控除を用いたご相談も承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。






